カラフル 放課後等デイサービス・日中一時支援
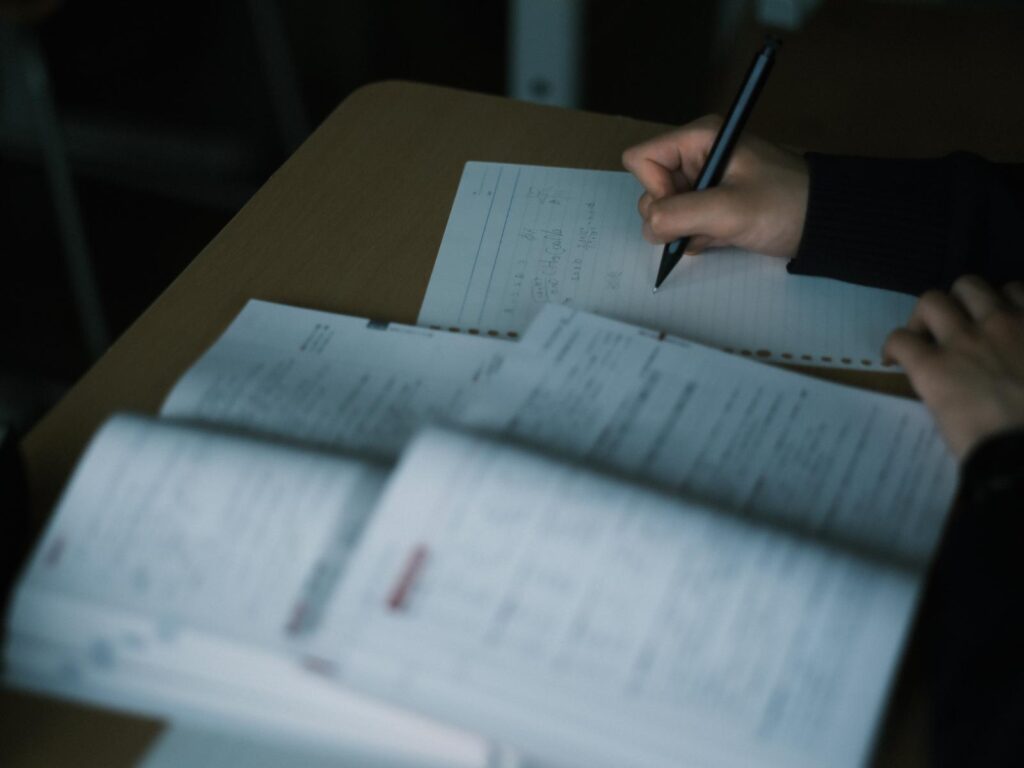
1. ゲームはなぜ頭を良くするのか?──脳科学からのアプローチ
ゲームをすると「頭が良くなる」。この言葉は直感的で魅力的だが、同時にどこか信じがたいですね。
特に「発達障害児にとってゲームが良い」と聞けば、なおさら眉をひそめる人もいるのではないでしょうか。
しかし、果たしてそれは単なる思い込みなのか、それとも認知科学的な根拠があるのか?
この問いに対して、私たちは一つひとつの前提を剥ぎ取りながら、脳の働きとゲーム体験の接点を探っていく必要があります。
本稿では、脳科学的な知見を軸に「ゲームはなぜ頭を良くするのか?」という命題を紐解き、さらに発達障害児にどのような可能性をもたらすのかを探求していきます。
■ 「頭が良くなる」とは何か?
脳科学における「頭が良い」は単純なIQの高さを指すのではなく、複数の認知機能の総合的な働きを指します。
- 記憶力(海馬)
- 判断力・計画力(前頭前皮質)
- 注意の持続と切り替え(実行機能)
- 空間認知(後頭葉・小脳)
ゲームがこれらの認知機能に与える影響を観察することで、その有効性を測ることができます。
■ ゲームと脳の構造変化
【Kühnら(2014)】による研究では、毎日30分間「スーパーマリオ」を2か月プレイした被験者の脳において、以下の部位で灰白質の増加が観察されました。
- 海馬(記憶力・空間認知)
- 前頭前皮質(意思決定・抑制機能)
- 小脳(運動制御)
この研究は、ゲームが神経可塑性(neuroplasticity)を刺激し、脳を物理的に成長させる可能性を示しています。
■ 実行機能と発達障害児
発達障害(とくにADHDやASD)の子どもたちは、「注意の持続」「感情制御」「計画的な行動」などに課題を持ちやすいとされます。
しかし、ゲーム、とくにアクションゲームや戦略ゲームでは以下のことが要求されます。
- 素早い判断
- 状況の変化への柔軟な対応
- 目標を達成するための段取り
- ミスをリカバリーする適応力
これはそのまま実行機能のトレーニングになると考えられます。
■ 報酬系とドーパミンの活性化
ゲームでは「クリアする」「レベルアップする」「ご褒美をもらう」など、即時報酬が明確です。
これにより、脳内のドーパミン分泌が活性化され、やる気・集中・反復行動が高まりやすくなります。
特にADHDの子どもはドーパミンの働きが弱い傾向があり、こうした即時報酬型の刺激によって「努力の報われる感覚」を得やすくなるのです。
■ 感覚統合への効果
- リズムゲーム:聴覚と身体の協応
- パズル系:空間認知
- 反応系:視覚・触覚の統合
発達障害児の中には「感覚のズレ(過敏または鈍感)」を持つ子が多くいますが、ゲームを通して感覚の統合的処理が練習できるとも言われています。

2. ゲーム時間の適切なコントロールと切り替え支援
■ 適切なプレイ時間の目安
- AAP(米国小児科学会):6歳以上の子どもは、1日2時間未満の総スクリーンタイムを推奨
- 日本の文部科学省・厚労省:可能であれば1時間以内が望ましい
ただし、単純に「時間が長い=悪」とは言い切れません。
本当に重要なのは、「何をしているか?」「どのように終えられるか?」という質と構造の問題です。
■ 発達障害児にとって「やめること」はなぜ難しいか
ADHDやASDの子どもたちは以下のような特性から、ゲームの切り替えが苦手です。
- 注意の持続ではなく注意の転換が困難
- 楽しいことに強く没入する傾向(過集中)
- 感情や行動の自己調整が苦手
- 予期せぬ中断への耐性が低い
■ 切り替えをサポートするための具体的工夫
① タイマーの「予告」型活用
- 開始時に「30分までね」と伝えるだけでなく、
- 残り10分/5分/2分の予告を段階的に入れる
- 視覚タイマーやタイムタイマーが有効
② 終了ルールの「事前合意」
- 「1ステージ終わったら」など、ゲーム内の区切りと連動したルールを明確化
- 紙に書いておく、終了カードを使う、親子で指切りなど儀式化が効果的
③ 「やめた後」のご褒美を用意
- 「終わったら好きなおやつ食べよう」
- 「一緒に折り紙しよう」
▶「終わる=楽しさが終わる」ではなく、「次の楽しみに移る」感覚を育てる
④ 終了の儀式を毎回固定
- 電源オフの前に「おしまいの歌」などを決めておく
- 「また明日やろうね」という再開可能性の提示も有効
⑤ 一緒にやめる
- 親もスマホや仕事をやめるタイミングを合わせ、「一緒にやめる経験」を共有する
- 「大人も我慢してる」と思えるだけで、子どもは納得しやすくなる
やめられない子を責める必要はなく、 脳の構造として「楽しいことをやめるのは苦手」ということを理解しましょう。 むしろ、やめられた時に 「えらいね」ではなく「自分でやめられたね」と伝えてみてください。 それが、自己調整力を育てる一歩になります。

3. アンチテーゼ:『ゲームは悪』という通念を問い直す
「ゲームは悪だ」「暴力的になる」「成績が下がる」「集中力が低下する」── このような批判は、テレビゲームの誕生以来、ずっと語られ続けてきました。
しかし、それらの主張は果たしてどこまで科学的根拠に基づいているのか?
あるいは、特定の条件下に限られた現象ではないのか?
そして何より、それはすべての子どもに当てはまるのか?
感情的に否定する前に、一つひとつを論理的に検証し、必要な部分に冷静に反論する姿勢を持ってみましょう。
■ ゲームで「暴力的になる」は本当か?
確かに、90年代以降の一部研究では「暴力的なゲームを遊んだ直後、一時的に攻撃性が高まる」という報告がありました(Anderson & Bushman, 2001)。
しかし、近年のメタ分析(Przybylski & Weinstein, 2019)では、
- 長期的な攻撃性との因果関係は見られない
- むしろ、「暴力的な映画」と「暴力的なゲーム」の影響に有意差はない
という結果も得られています。
▶ 結論:ゲームが人を暴力的にするという主張は、統計的には一貫性に欠ける
■ ゲームが「成績を下げる」は本当か?
「ゲームに夢中で勉強しない」ことが問題なのではなく、
「勉強が苦手で達成感を得られない子どもが、ゲームに逃げる」という構造の方が本質的です。
また、戦略ゲームやパズルゲームは以下のような認知能力を高めるとされています:
- 論理的思考
- 空間認知
- 課題解決能力
▶ 教育的に設計されたゲームは「学力を補完する存在」にもなり得る
■ 集中力が低下する?
アクションゲームにおいて、以下の能力が訓練されることが報告されています:
- 注意の分配と持続
- 情報処理速度
- 視覚的な選択的注意(Green & Bavelier, 2003)
特に、ADHD児においてはゲームが「集中力のトレーニング」として活用される例もあります。
▶ 適切なゲームは、むしろ集中力を高めることすらある
■ 依存のリスクは?
これは無視できません。
ただし、それはゲームに限ったことではなく、SNS・食・ギャンブル・買い物でも同様です。
依存とは、「目的を失った反復」です。
逆に言えば、意味を持ってゲームを使い、社会や自分との接点を保てていれば、それは依存ではありません。
ゲームにネガティブな側面があるのは事実。 だがそれは「すべてが悪」という意味ではありません。
火は危ないが、料理にも暖房にも使える。
ゲームもまた、扱い方によっては脳を鍛え、心を育てるツールになる。
大人ができるのは、禁止ではなく、賢く選ぶ支援であると言えるでしょう。

4. ゲームに潜むリスクとそのリスクヘッジ──正しく恐れ、賢く付き合うために
ここまで、ゲームのポジティブな側面に焦点を当ててきました。 しかし、それは「ゲームは常に良い影響をもたらす」という意味ではありません。
むしろ、ゲームの恩恵を受けるには、潜むリスクを理解し、それを回避する知恵と構造を用意することが前提となります。
恐れるべきは、ゲームそのものではない。「知らずに放置すること」なのです。
■ 主なリスクと対処法
① 依存のリスク
● 問題点
- 過度なプレイによる日常生活の崩壊(食事・睡眠・学業の欠如)
- ゲーム以外への興味の喪失
- 現実世界での自己肯定感の低下
● 対処法(リスクヘッジ)
- 「ゲームの前にやるべきことを終わらせる」ルールを固定化
- 他の楽しみ(外遊び、創作、会話)を日常に組み込む
- ゲームの内容を言語化・共有し、親や支援者とつながる時間に変える
② オンラインチャットのトラブル
● 問題点
- 他者との暴言・いじめ・排除行為
- 誘導・詐欺・性被害など深刻なケースも
- 発達障害児は、言語や感情のニュアンスを読み違えやすいため、被害に遭いやすい
● 対処法
- 小学生まではオフラインプレイを中心に
- オンラインは、親がチャット履歴を確認できる環境のみ許可
- チャット機能は「知っている人だけと」「親と一緒に」など条件付きで解禁
- ペアレンタルコントロール機能の活用
③ 過刺激・睡眠障害
● 問題点
- 光や音の刺激による覚醒状態の持続
- 睡眠の質の低下
- 昼夜逆転
● 対処法
- プレイは遅くとも18時までに制限
- 終了後は本を読む/お風呂に入る/暗い部屋で静かに過ごすなど、就寝への移行儀式を取り入れる
- ブルーライトカットモードの使用
④ 現実との乖離・自己肯定感の偏り
● 問題点
- ゲームの中だけが「自分が認められる世界」になってしまう
- 現実での不安や失敗から逃げ続ける傾向に
● 対処法
- 「ゲームで得た力を現実に接続する」言葉がけを意識
- 例:「その工夫、自由研究に活かせそうだね!」
- 「この集中力、他のことでも使えそう!」
▶ 現実とゲームの成功体験をブリッジさせる発想が重要
ゲームは頭を良くするのに便利な道具です。 でも、包丁も便利ですが研がなければ切れず、使い方を間違えればケガをしてしまいます。
子どもにとってゲームとは、「社会」と「自分」を安全に試す場でもあります。
そこに潜む危険をあらかじめ見つけ出し、「安全に試せる構造」を用意するのが、大人の役目と言えます。
禁止するより、一緒にリスクを言語化する方が、子どもはゲームの世界でも、現実の世界でも、強くなっていくのではないでしょうか

5. マインクラフトという創造的学習空間
思考の旅の終着点に、今ひとつの象徴的存在を挙げておきます。 それは――マインクラフトです。
このゲームは、単なるブロック遊びではありません。
現代における「創造的認知機能の総合トレーニング空間」として注目されています。
子どもたちはなぜ、マイクラにこれほどまでに惹かれるのでしょうか?
そして、それが発達障害児にとって、どのような意味を持つのでしょうか?
それでは、掘り下げてみていきましょう。
■ 空間認知と構成力の強化
マインクラフトでは、プレイヤーが自由に建築物や仕掛けを作ります。
その過程では、3D空間上での配置や構成を考えながら手を動かす必要があります。
これは、視空間認知力・計画力・操作の統合力を育む作業です。
特にASD傾向のある子どもたちは、この「パターン認知」や「構造の把握」に長けており、自分の得意を発揮できる貴重な場となります。
■ 実行機能の自然なトレーニング
- 材料を集める(段取り)
- 建築を設計する(計画力)
- 失敗を修正する(柔軟性)
これらの一連のプロセスは、「実行機能(Executive Function)」を多角的に育む効果があります。
とくにADHDの子どもにとって、「小さなゴールに向かって段階的に取り組む」という体験は希少であり、自己効力感(やればできる)の育成に直結します。
■ 自己決定と創造の自由
マインクラフトには明確な「勝ち負け」や「ルールによる制限」がありません。
だからこそ、自分で目的を決めることになります。
- 今日は農場を作る
- 明日は地下に基地を掘ってみる
- 仲間と村を作る
▶ この「自分で決める→形にする→完成する」という流れは、有能感・自律性を大いに満たします。
■ 社会性の別ルート:マルチプレイの可能性
マインクラフトは、マルチプレイでの協働も可能です。
- 役割分担(資源集め・建築・守備など)
- チャットでのコミュニケーション
- 相手のアイデアを取り入れて共同で建築
これらの体験は、言語中心でない関係性の構築を可能にし、対人不安のある子どもにとっては「別ルートの社会性」を育むきっかけになります。
■ 論理と創造の接点:レッドストーンと自動化
さらに進めば、「レッドストーン回路(仮想電気回路)」を使って以下のような装置を作ることも可能です。
- 自動ドア
- トラップ
- 計算機やパズル装置
これはプログラミング的思考の実践であり、「創造性 × 論理性」の融合がここにあります。
マインクラフトは、子どもにとってただの遊び場ではないのです。 それは、「自分の世界を自由に作ってよい」と許される、安全な空間であることを示しています。
現実で「できない」と言われたことも、この世界では「試してみよう」と思える。
発達に課題を抱える子どもたちにとって、そのように思える世界がひとつでも増えること。
それこそが、ゲームが持つ最大の教育的価値なのではないでしょうか。
