カラフル 放課後等デイサービス・日中一時支援
はじめに
子どもが突然大声をあげて泣きわめいたり、物を投げたり叩いたりする「癇癪(かんしゃく)」。
発達障害のある子どもにしばしば見られる行動ですが、実際に関わる家族や支援者にとっては大きな課題です。
「どうしてこんなに怒るの?」「わがままなの?」と戸惑ってしまうこともあるでしょう。
しかし、脳科学の視点で癇癪を理解すると、それは単なる「わがまま」や「性格」ではなく、脳の仕組みからくる自然な反応だとわかります。そして適切に対応していくことで、少しずつ癇癪は減っていく可能性があります。
本記事では、脳科学の知見をもとに、癇癪が起こる理由と対処法、そして長期的に癇癪を減らしていくための工夫を解説していきます。
癇癪が起こる脳科学的な理由
1. 前頭前野の未発達
脳の前方にある「前頭前野」は、人間が感情をコントロールしたり、状況を見て行動を選択したりする働きを担っています。大人であれば「ここで怒っても仕方ない」と判断して怒りを抑えられますが、子どもは前頭前野が未発達なために感情を制御する力が弱いのです。
発達障害のある子どもでは、この前頭前野の発達や機能の働きがよりアンバランスになっていることが報告されており、そのため癇癪が爆発的に表れやすくなります。
2. 扁桃体の過敏さ
脳の奥深くにある「扁桃体」は、不安や恐怖、怒りといった感情に関わる部分です。発達障害のある子どもでは、この扁桃体が過敏に働くことがあり、わずかな刺激でも「危険だ!」と脳が反応してしまいます。
結果として「嫌だ」「怖い」「思い通りにいかない」という体験が強烈に表れ、癇癪として爆発します。
3. 感覚過敏と情報処理の困難
発達障害の子どもには、音・光・匂いなどに過敏な反応を示す「感覚過敏」がよく見られます。脳に過剰な情報が一気に流れ込み、処理しきれなくなると、ストレスが溢れ出して癇癪につながります。
例えば、スーパーのざわざわした音や蛍光灯の光が耐えられず、突然泣き叫ぶケースもあります。
4. 神経伝達物質の影響
ドーパミンやセロトニンといった神経伝達物質は、気分や行動を安定させる働きを持っています。発達障害ではこれらの働きが不安定になることがあり、そのため感情の起伏が激しくなり、癇癪の引き金になりやすいと考えられています。
癇癪が減っていく脳のメカニズム
「癇癪は一生続くの?」と不安になる保護者も多いでしょう。脳科学的には、癇癪は成長とともに減っていく可能性が高いといえます。
- 経験による学習
繰り返しの経験を通して前頭前野の「ブレーキ機能」が少しずつ鍛えられ、感情を抑える力が育ちます。 - 安心できる環境
安全で安心できる環境にいると、扁桃体が過敏に反応することが減り、落ち着きやすくなります。 - 言葉や表現の習得
自分の気持ちを言葉や行動で伝えられるようになると、癇癪という爆発的な表現に頼らずに済むようになります。
脳科学に基づいた具体的な対処法
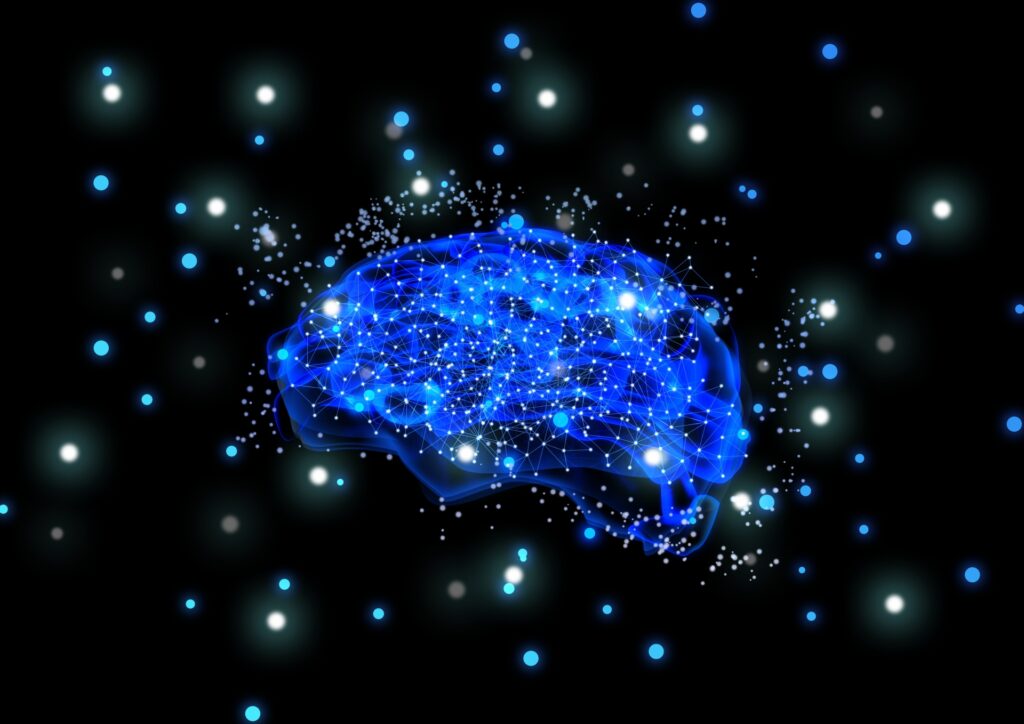
1. 癇癪を予防する工夫
- 見通しを与える
「あと5分で終わり」「次は○○だよ」と予告することで脳の混乱を防ぎます。 - 感覚刺激を減らす
音を遮るイヤーマフやサングラスを使うなど、感覚過敏を和らげる工夫が有効です。 - ルーティンを活用
毎日の流れを安定させることで、予測不能な状況に弱い脳への負担を減らせます。
2. 癇癪が起きたときの対応
- 安全の確保を第一に
自分や他人を傷つけないよう、危険な物を避けて落ち着ける環境に誘導します。 - 説得は逆効果
扁桃体が強く反応している状態では、言葉は届きません。まずは沈静を待つことが大切です。 - クールダウンの方法
静かな場所に移動する、抱きしめる、深呼吸を促すなど、子どもに合った方法を探しておくと効果的です。
3. 長期的に癇癪を減らす支援
- 感情ラベリング
「怒ってるんだね」「悲しいんだね」と言葉にしてあげることで、前頭前野の働きが促されます。 - 小さな成功体験
できた!褒められた!という体験は、脳の報酬系を活性化し、安心と自己肯定感を育みます。 - 認知行動療法やSST
専門的な支援を通して「感情の扱い方」「他者とのやりとりの練習」を積むと、癇癪が減りやすくなります。
家庭や支援現場での工夫
癇癪をなくそうとするよりも、「脳の仕組みに合わせて支える」ことが大切です。
- 親や支援者が落ち着いて対応することで、子どもは「安心の信号」を受け取ります。
- 癇癪は「脳が学習している途中のサイン」でもあります。焦らず長期的に見守る姿勢が必要です。
- 学校や放課後等デイサービスなど、関わる大人が連携して「共通の対応」を取ることも効果的です。
まとめ
癇癪は「わがまま」ではなく、脳科学的な理由に裏打ちされた自然な反応です。
前頭前野の未熟さや扁桃体の過敏さ、感覚過敏や情報処理の困難が背景にあり、脳が安心と予測可能性を求めているのです。
大人ができることは「怒る・叱る」ことではなく、脳の仕組みを理解して支えること。
予防・対応・長期的支援を組み合わせることで、癇癪は少しずつ減っていきます。
癇癪に悩む日々は、子どもと一緒に脳が成長している過程そのもの。焦らず、科学に裏づけられた方法で、子どもとともに歩んでいきましょう。
