カラフル 放課後等デイサービス・日中一時支援
はじめに
人生は、思いがけない出来事や心が揺れる瞬間の連続です。
誰にとっても、失敗したり、人に批判されたり、思い通りにいかなかったりすることがあります。そんな時に心を守り、もう一度立ち上がる力をくれるのが「精神的な砦」です。
支援の現場でも同じことが言えます。発達障害のある子どもたちには、不得意なことを一つずつ克服していく支援が有効な場合もありますし、それを大切にしている施設も多くあります。けれど一方で、「できること」「好きなこと」を見つけて伸ばす支援もあります。どちらか一方ではなく、子どもに合ったアプローチを選びながら、安心して戻れる“心の基地”を育てることが大切なのです。
1. 「精神的な砦」とは何か
「砦」とは、外からの攻撃にさらされても守られる拠点です。精神的な砦は、外の出来事に揺さぶられても、自分を取り戻せる心の基盤のことを意味します。
これは防御のための壁ではなく、「戻れる場所」。子どもにとっては「自分の得意分野」「成功体験」「安心できる人とのつながり」がその砦になります。そこに戻ることで心を整え、再び挑戦できる勇気を得られるのです。
2. 砦を持つことのメリット
子どもにとって精神的な砦を持つことには、いくつかの大きなメリットがあります。
- 失敗や批判から立ち直る力(レジリエンス)が育つ
挑戦すれば失敗はつきものですが、砦があることで「自分には戻れる場所がある」と感じられ、挫折しても再び立ち上がれるようになります。これは心理学でいうレジリエンス(回復力)を高める効果があります。 - 自己肯定感が揺らぎにくくなる
不得意なことに直面したときでも、「自分にはこれができる」という得意分野があると、全体的な自己評価が下がりにくくなります。砦は「自分の強みの象徴」として、心を守ってくれます。 - 自己肯定感が低い子にとっての支えになる
発達障害のある子の中には、「どうせ自分はできない」「また失敗する」と感じやすく、自己肯定感が低くなりがちな子も少なくありません。そうした子にとって、砦は「自分にもできることがある」「この分野なら自分らしくいられる」という確かな証明になります。この実感があることで、否定的な自己イメージに引きずられず、少しずつ自信を回復していくことができます。 - 挑戦する勇気が持てる
砦がなければ、「失敗したら終わり」という恐怖で挑戦を避けてしまいます。砦があれば、たとえうまくいかなくても戻れる安心感があるため、新しいことに挑戦できる勇気が生まれます。 - 長期的な学びや成長が持続する
特性を伸ばすことを砦にできれば、学びや体験が単発で終わらず、継続して積み重なっていきます。これは「学習の持続可能性」を高める役割を果たします。
3. 「できることを伸ばす」支援の意義

発達障害の子どもたちに対する支援には大きく二つの方向があります。
ひとつは「できないことを克服する」こと。たとえば苦手な読み書きやコミュニケーションを少しずつ練習していく支援です。これは確かに社会生活を送るうえで必要であり、大切な取り組みです。
もうひとつは「できることを伸ばす」支援。得意なことや好きなことを深めていくアプローチです。最新の研究でも、「特性を生かして成功体験を積むことが自己肯定感を高め、ひいては社会適応力を育てる」とされています(文部科学省 特別支援教育調査研究報告, 2022 / J-STAGE「二重に特別な子どもの教育」2023)。
特に「2E児(二重に特別な子ども)」と呼ばれる、発達障害と高い才能を併せ持つ子どもに対しては、「不得意を補うより得意を伸ばす方が長期的に適応を高める」という指摘もあります。
4. カラフルスクールの理念と精神的な砦
千葉県浦安市を拠点に展開する「放課後等デイサービス・日中一時支援カラフル」では、この「できることを伸ばす」支援を中心に据えています。公式サイトで掲げられている理念は、まさに子どもたちにとっての精神的な砦を築くものです。
- 楽しいから続けられる
MinecraftやRobloxなど、子どもたちが夢中になれる題材を活用し、「楽しい」という気持ちを出発点に学びを持続させます。楽しさこそ、心を支える砦の第一歩です。 - 成功体験を積み重ね、自己肯定感を育む
小さな達成を積み重ねることで、「自分はできる」という実感を持たせます。この成功体験の積み重ねが、困難に直面した時に戻れる精神的基盤になります。 - 自分の言葉で表現を
作品発表やプレゼンテーション、ディベートを通じて「自分の意見を伝える場」が設けられています。これは、自己存在を確認できる場=砦の役割を果たします。 - 思考のトレーニング
ロボットプログラミングやLEGO教材を通じて、論理的思考や協調性を鍛えます。これは砦をより強靭にし、挑戦するための足場を固めることにつながります。 - 個性の発見と未来の選択肢
一人ひとりの「好き」を発見し、それを未来につなげていく。自分らしい進路の幅が広がることで、「自分には未来がある」という確信が砦となります。
5. エビデンスと理論的補強
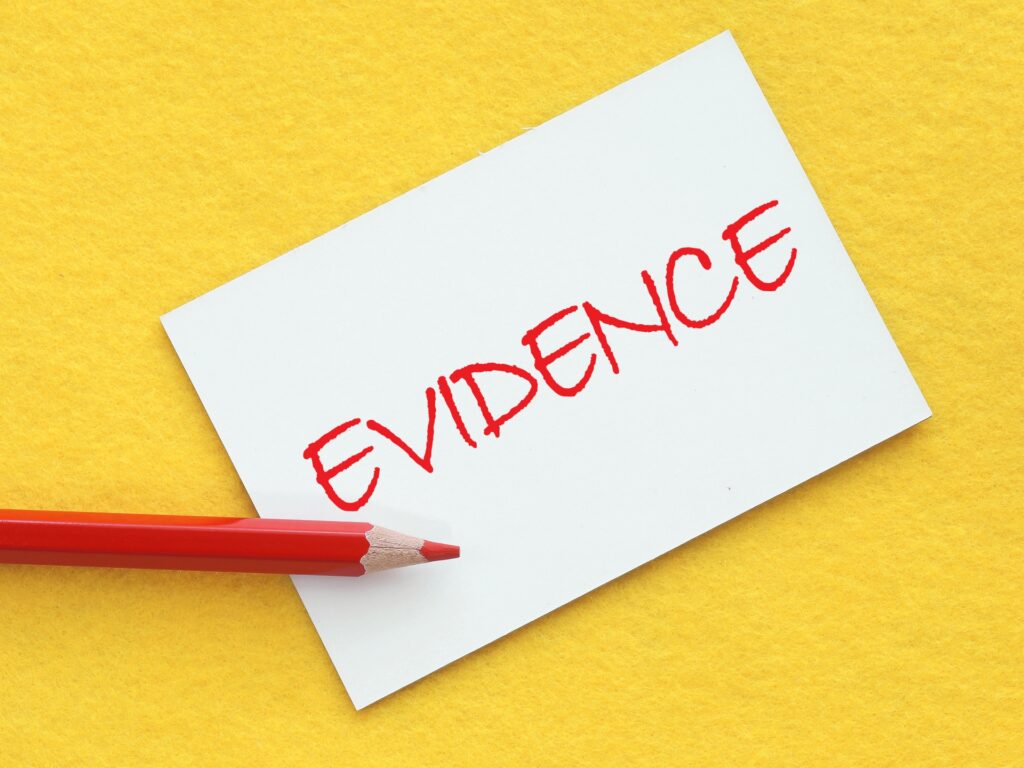
- 安心できる環境が二次障害を防ぐ
発達障害の特性自体が問題なのではなく、否定され続ける環境が二次障害を引き起こすと報告されています(国立特別支援教育総合研究所, 2020)。安心できる場と関係性があれば、適応状態は安定し、砦として機能します。 - 生活モデルに基づく支援の有効性
医学的に「治す」ことより、生活の場で「育てる」支援が効果的であるとされます(J-STAGE「発達障害支援の生活モデル」2021)。カラフルが提供する「日常に即した成功体験と楽しさの場」はこのモデルに合致しています。 - 得意を伸ばすことで不得意を補える
「強みベースの支援」は、不得意領域を直接鍛える以上に、結果的に日常生活での自立を後押しすることが示されています(トヨタ財団研究助成報告, 2019)。これは「砦=得意分野」が防波堤の役割を果たすことを裏付けています。
まとめ
発達障害の子にとっての「精神的な砦」とは、外からの揺さぶりを遮断する壁ではなく、困難に直面した時に戻ってこれる“心の安全基地”です。
不得意を克服する支援も大切ですが、同時に「できることを伸ばす支援」を通じて砦を築くことができます。特に自己肯定感が低くなりがちな子にとっては、この砦が「自分らしくいられる場所」となり、未来への挑戦を後押しします。
カラフルスクールの理念は、その両者を認めながらも特に「できること」に光を当てる実践例であり、子どもが自分自身を肯定し、未来に向けて挑戦できる環境を整えています。
私たち大人ができるのは、子どもたちが安心して戻れる砦を一緒に育て、そこから何度でも挑戦できるよう支えることです。そうすれば、子どもたちは「できる自分」を信じ、力強く生きていくことができるでしょう。
